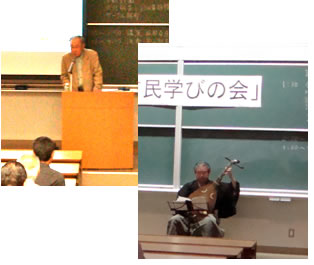名古屋市立大学人文社会学部・大学院人間文化研究科「市民学びの会」は、2007 年 9 月に発足して幅広い活動を続けている。「学びたい市民」と「市民に学ぶ場所・機会 を提供する名古屋市立大学」を結ぶ市民主体の団体である。 5 月 23 日午後、名古屋市立大学滝子キャンパス 1 号館 201 教室で「市民学びの会」 恒例の企画が開催された。懐かしい教室には多くの参加者が詰めかけた。
今回のテーマ は「戦後70年、今一度あの戦争を考える」 である。 まず、ノンフィクション作家の大野芳 さんが「開戦前夜の近衛文麿」について 講演した。話の始まりは「貴公子近衛文 麿」であり、2・26 事件から近衛内閣の 誕生、日米交渉と御前会議、開戦へと続 く。短い時間の講演のなかで、大野さん 独自の「史観」も披露され、多くの論点 を提起する講演であった。
その後、大野 さんと当会代表理事の門池啓史さんとの対談となり、講演で提起された論点がどのよう に深められるか期待して耳を傾けた。 対談のテーマは「開戦直前の日米関係」である。配布資料の年表やキーワード解説も 交え、ハルノートや太平洋戦争勃発に至る経過がいくつかのエピソードの紹介を含めて 議論される。近衛文麿や松岡洋右、木戸幸一などの「人物像」、開戦前夜から日米開戦 に至る経過など、二人の見解、「史観」は異なるところも多かった。議論がかみ合わず、 それが対談を面白くもさせていた。見解の相違は当然として、企画の趣旨がもうひとつ 分かりにくかったことが、「辛口コメンテーター」として残念であった。
戦後 70 年、今一度あの戦争を考えること、悲惨な戦争に至る歴史を振り返ることは、 大切な課題であるのは言うまでもない。門池さんは「もう一度学ぼう太平洋戦争への道」 というテーマで、市民学びの会「戦争シリーズ」を続けてきた。今回の講演と対談は、 その一環として企画されたようだ。なぜ太平洋戦争に至ったのか、戦争を防げなかった のかを、隠された資料を発掘し、歴史的事実を明らかにすることは重要な課題だ。その 際、戦争をどのように評価するか、「戦争史観」が問われることになる。講演や対談で、 この点があいまいなまま議論されたのに、いささか違和感をもった。 大野さんが講演のなかで「長州がキ―ワ―ド」と繰り返していたのが印象深い。戦後 70 年、戦後政治とりわけ戦争との関わりを考えると、岸から安倍へと「長州」が再び 注目を集めているようだ。この点を含めて質問しようとしたが、つい遠慮してしまった。
(2015 年 5 月 25 日 山田明名誉教授)